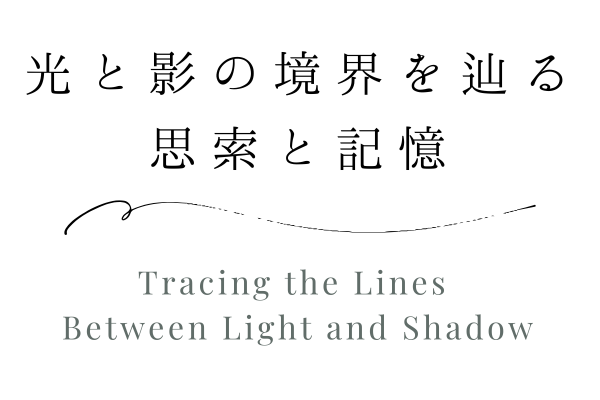わたしは花や植物が大好きだ。
チェンマイに来てからは「庭を作る」ということはしていない。というか、あの広い敷地には勝手にいろいろ咲くし(笑)、暑さでこっちが先にヘタる。だから最近は、手を入れるよりも「眺めて受け取る」ほうが多いかもしれない。
それでも日本やアメリカで暮らしていた頃のわたしは、ちょっとした Green Thumb のガーデナーだった。土の匂い、葉の厚み、季節の光の角度――そういうものが生活の中心に自然と入ってくる暮らしが好きだった。住まいを選ぶときも、緑が豊かな場所であることは、最初に確認する大事な条件のひとつだった。
花を見て「美しい」と感嘆するとき。
自然の中で大きな木に抱かれるような感覚になるとき。
風に揺れる葉のざわめきや、雪解けの水音に耳を澄ますとき。
ありえないような色に染まる朝と夕の空、満天の星の気配に圧倒されるとき。
そういう瞬間は、とても瞑想的だ。
頭の中の言葉が、説明や判断が、いつのまにか後ろへ下がっていく。
そして自分が「静かになっている」ことに、あとから気づく。
自然の中で心が鎮まる、ということをはじめてはっきり体験したのは、アフリカに住んでいた頃だった。コロラドの森の中で暮らしていた時期は、まさにそれを日々の空気として吸っていたように思う。
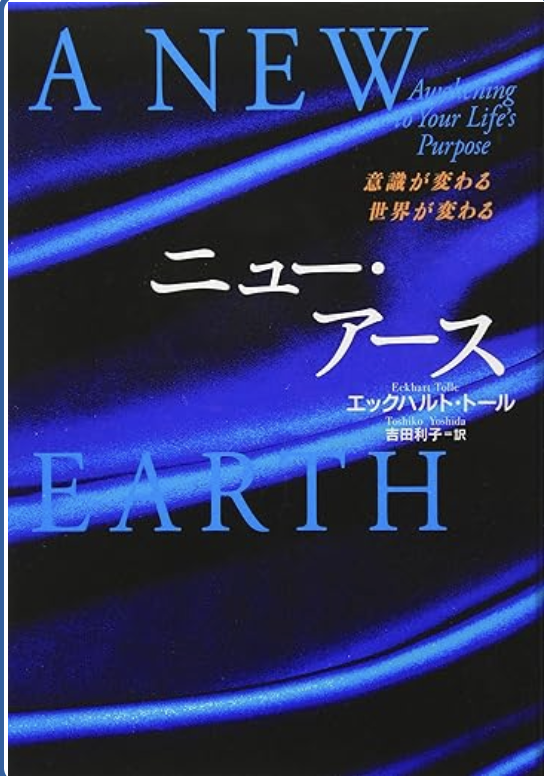
最近、恥ずかしいほどに何度も読み返している本がある。エックハルト・トールの『ニュー・アース』だ。
「何も新しいことは書いていない」と言ってしまえばそうなのかもしれない。でも、今の自分に必要な言葉が、必要な順番で、必要な温度で置かれている。読んでいると「そうなんだよ」と、理解が頭ではなく身体に落ちてくる感じがする。
その本の冒頭に、花の話が出てくる。
人が花の美しさに心を奪われるとき、わたしたちは一瞬でも思考の外に出て、「自分の内側の本質」に触れる――そんな趣旨のことが語られている。
花という形あるものを見ながら、形にならないもの(静けさ、喜び、愛、生命の聖なる気配)に触れてしまう。だから花は、言葉で説かなくても、こちらの意識を「今」へ連れ戻してしまうのだ、と。
この感覚は、わたしの記憶の中にそのまま残っている。
コロラドの山奥暮らし。長く厳しい冬が終わって、雪解けと同時に野草が一斉に咲き始める季節。
野の花たちはとても儚い。今日ここに咲いているのに、明日にはもう姿が変わっている。ときには、翌日に「夏の積雪」だの「低温・遅霜注意報」だの、こちらが心配になるような予報が出ることもある。けれど花は、そんなことを一切思い煩っていない。
ただ、風に揺れている。
ただ、その瞬間を生きている。
「咲く」という役割を演じているのではなく、咲いているという在り方そのものになっている。
わたしはその姿に、心底、打たれる。
そして面白いことに、そうやって見入っている時間のあいだ、わたしの頭の中の「絶え間ないおしゃべり」が止まっている。
花がわたしを黙らせるのだ。――いや、「黙らせる」というより、黙ってしまう場所へ連れていく、と言ったほうが近い。
思考が静かになると、そこに別のものが顔を出す。
理由のない、条件のいらない、説明不要のあたたかさ。
花と向き合っていると、わたしの内側から、無条件の愛が立ち上がってくるのを体験する。こちらが良い人になったからではない。ただ、余計なものが引っ込むから、もともと在ったものが見える。
クリシュナムルティは、花を前にして「何かをしようとしなくていい。ただ心を開いて見つめなさい」というようなことを語ったという。
本当に、その通りだと思う。
花の前では、修行も努力も、立派な思想もいらない。こちらが武装を解いた瞬間に、花はすでに教えている。
逆らわないこと。
あるがままで素晴らしいこと。
そして、愛。
花は黙って、それを示してくれる。
わたしにとって花は、「神聖」という言葉が現実味を持つ、数少ない存在のひとつだ。
今日もし道端で、名も知らない小さな野の花に出会ったら、ほんの数秒でいい。
説明を始める前に、判断を挟む前に、まず見つめてみよう。
花は、いつでも先に「在り方」で答えている。